障害者への暴力・殺害に関する記述を含みます
近年、日本でも「日本人ファースト」といった排外主義的な言説や、外国人労働者受け入れ政策への不満が広がっています。 同時に、社会保険料の上昇や生活保護費に対する国民のいら立ちも目立つようになっています。
20世紀前半のドイツでは、優生思想が政策と医学に入り込み、精神障害者が「生きるに値しない命」とされました。 そしてそれは国家的な殺害プログラム(T4作戦)へと発展します。現代日本をそのまま重ね合わせることはできませんが、 過去に何が起きたかを知ることは、現在の議論を冷静に進めるための最低限のリテラシーだと考えています。
本稿は感情を煽るためではなく、負担/効率の語が肥大するときに何が起きたかを、史実で確認する試みです。 その手がかりとして、ナチス期の精神科患者に対する断種・殺害を数量的に検討した Torrey & Yolken (2010) を読み解きます。
この論文が示す事実(要点)
- 断種:1934–45年に約40万人。少なくとも約13.2万人が統合失調症。
- 殺害:総計20万〜27.5万人。うちT4作戦(1940–41年)のガス殺だけで70,273人。
- “根絶”は起きなかった:戦後ドイツは有病率は低い一方で発症率は高いという非対称が持続。
参考:Torrey EF, Yolken RH. Psychiatric Genocide: Nazi Attempts to Eradicate Schizophrenia.DOI:10.1093/schbul/sbp097 / PMC
以下では、①国際的文脈と法制度、②T4の仕組み、③規模の推計、④戦後疫学、⑤現代への含意の順に、 「数字で分かる歴史」として要点を追っていきます
用語の定義と扱う範囲
優生学とは、遺伝を名目として国家が生殖や生命の価値を選別する政策群を指します。
政策としての医学とは、医療専門職が国家目的に動員され、倫理より政策合理性が優先される状態を指します。
- 時間範囲:1880年代〜1950年代(T4と戦後初期の疫学まで)
- 地域:主としてドイツ(必要に応じて米英の優生政策に触れます)
- 対象:精神障害者、とくに統合失調症
- 主題:制度史/断種・殺害の規模推計/戦後の有病率と発症率
- 除外:ホロコースト全体史や遺伝学技術史の詳細、倫理哲学の総論
国際的文脈:米英の優生運動からドイツへ
20世紀初頭、強制不妊法は米国や英国で先行しました。ドイツ語圏の「人種衛生」思想はこれらと結びつき、 ドイツの研究者や政策担当者、医師層に強い影響を与えました。こうした潮流が、のちの法制度化の素地となりました。
精神医療の逼迫とT4作戦に至るまで
第一次大戦後、賠償と不況でドイツ国家財政が逼迫し、精神医療費の削減が優先課題となりました。政策議論では〈権利〉より〈コスト〉が強調され、医療は「収容費の圧縮」という物差しで語られるようになっていきます。
1920年、法学者バインディングと精神科医ホッホは、慢性精神疾患などを「法の保護に値しない生命」と位置づけ、殺害の正当化を論じました。 この議論は、国家財政の観点から「経済的負担」を理由に生命の価値を区別するロジックを後押しし、社会に広がっていきました。
さらに同時期の学界では、人種衛生/優生学の潮流の中で統合失調症を遺伝的に受け継がれる疾患とみなす見方が力を持ち、診断の重心がここに寄りました(Rüdin/Kallmann ら)。 1933年の「遺伝病子孫防止法」は統合失調症を名指しで断種対象に含め、過密化した病院では退院予定の患者が優先的に断種される運用が広がりました。
こうした学説と制度がかみ合い、現場では病床が急速に埋まっていきました。入退院の回転を速めても満床が常態化し、 病棟内で統合失調症とされる患者の比率が上昇しました(ある病院では40%台から過半へ、新規入院の約3分の2が同診断と報告されています)。 つまり、学説(遺伝) → 制度(断種) → 現場(満床と比率上昇)が相互に強化し合い、「統合失調症」というラベルの使われ方そのものが拡大していったのです(Torrey & Yolken, 2010)。
*「退院予定の統合失調症患者を断種すれば病床は空くのでは」という疑問が生まれやすいのですが、断種はそもそも 将来の出生を防ぐ政策であって、いま病棟にいる患者さんの数を減らす施策ではありません。 当時は退院後の受け皿が乏しく、慢性患者さんは行き場がなくて入院が続きました。さらに、経済困窮と収容中心の運用で 入院の流入が恒常的に上回り、満床は解消しませんでした。実際に病床が急減したのは、1940〜41年の T4作戦やその後の病院内殺害によって物理的に患者数を減らしたためであり、断種だけでは病床は空かなかったのです。
1939年の転回:T4作戦の発動
1939年9月1日付のヒトラー書簡を根拠として、ベルリン・ティアガルテン通り4番地(T4)に本部が設置されました。 全国の精神病院から提出させた疾患名と労働能力のみ記載された診断票のみで約7万人の殺害目標が設定され、移送や転院の名目で患者が選別されました。 家族には偽の死因が通知されるなど、制度的な隠蔽が組み込まれていました。
殺害のロジスティクス:ガス室・注射・飢餓
1940年、まずブランデンブルクで一酸化炭素ガスによる殺害が開始されました。 続いてベルンブルク、グラーフェネック、ハダマール、ハルトハイム、ゾンネンシュタインに6つの殺害中枢が設置され、1941年8月までに70,273人が殺害されました。 その後も病院単位で致死量の注射や飢餓が組織的に用いられ、小児も対象となりました。
規模の算定:断種40万/殺害20〜27.5万
- 断種:1934〜45年に約40万人。うち少なくとも3分の1(約13.2万人)が統合失調症でした。
- 殺害:総計20万〜27.5万人。うち1940〜41年のガス殺で70,273人、ほかに飢餓や注射による死亡が多数でした。
- 病院在院数の激減:1939年28.3万人→1945年4万人(14%)へと急減しました。
- 統合失調症に限る合計:22万〜26万9,500人が断種または殺害(当時の該当者の73〜100%)と推計されます。
戦後ドイツの疫学:有病率は低く、発症率は高い
- 有病率:マンハイムの症例登録(1974〜80年)では1年有病2.3/1000で、同時期の英国(3.4/1000)や米国(4.7〜5.1/1000)より低い水準でした。
- 発症率:マンハイムでは1965年に53.6/10万人/年、1974〜80年は48〜67(平均59)/10万人/年で、国際比較の平均(約24/10万人/年)より高い値が報告されています。
つまり、「遺伝的に消す」発想は統計的に支持されなかったということです。統合失調症は多遺伝子と環境要因(出生周辺の低酸素、栄養、感染など)の相互作用で生じると理解されており、単純な「淘汰」で発症率を下げることはできませんでした。
年表:断種からT4へ
- 1933年7月:「遺伝病子孫防止法」が成立します。統合失調症・躁うつ病・てんかん・重度知的障害などが断種(強制不妊)の対象になります。
- 1934年1月〜:全国の「遺伝衛生裁判所」で審理が始まり、1934〜45年に約40万人が断種されます(うち少なくとも約13.2万人が統合失調症とみなされます)。
- 1939年9月:ヒトラーの書簡を根拠に、精神科患者の殺害プログラム(T4)が準備されます。
- 1940〜41年:6つの中枢施設でCOガス殺が実施され、70,273人が殺害されます。
- 1941年8月以降:T4は公式には停止しますが、病院内での注射・飢餓による殺害が各地で継続します(小児も対象)。
出典:Torrey & Yolken (2010) ほか。
現代への警鐘
今回は、当時「精神病者」と分類された人々に向けられた国家的暴力の記録をたどりました。
「負担を減らす」は正しく聞こえます。しかし、費用は線を引く口実にもなります。 線は、いつも弱い側に引かれます。歴史はそうでした。
科学は万能ではありません。診断も遺伝も確率です。確率で人を切らない。これが第一原則です。 次に、数字の出所を明かし、反証可能にする。最後に、切り捨てる前に支える手段を尽くす。
それだけで、坂道は滑り台になりません。
参考文献
- Torrey EF, Yolken RH. Psychiatric Genocide: Nazi Attempts to Eradicate Schizophrenia. Schizophrenia Bulletin. 2010;36(1):26–32. doi:10.1093/schbul/sbp097
- Lifton RJ. The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide. Basic Books; 1986.
- Friedlander H. The Origins of Nazi Genocide: From “Euthanasia” to the Final Solution. University of North Carolina Press; 1995.
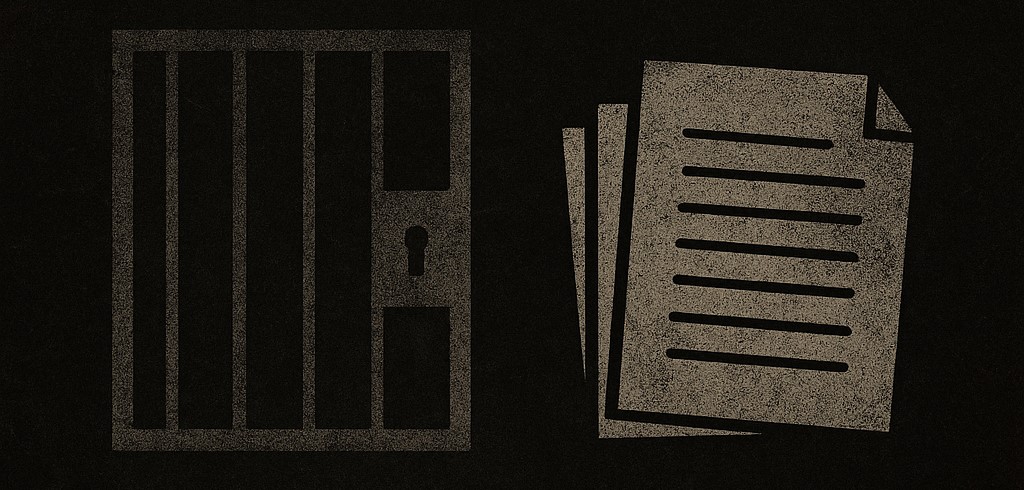


コメント